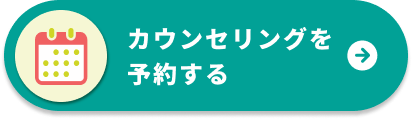共依存とは?陥りやすい人の特徴や原因、抜け出すための克服方法を解説
人間関係に悩みを抱えている人も多いでしょう。相手との関係性が知らないうちに深刻な状況に陥っていて、気がついたときには抜け出せないといった経験はないでしょうか。共依存もそのひとつ。
この記事では、共依存と定義される状態や、共依存に陥りやすい人の特徴についてわかりやすく解説しています。また、共依存から抜け出すための方法も複数挙げていますので「もしかして共依存かも?」と心当たりがある人は参考にしてください。
共依存とは

厚生労働省が運営する生活習慣病予防のための健康情報サイト「e-ヘルスネット」によると、共依存とは「依存症者に必要とされることに存在価値を見いだし、ともに依存を維持している周囲の人間の在り様」と定義されています。
共依存は、英語で「Co-Dependency」と表記され、Coは同等・共同、Dependencyは依存症という意味を持ちます。共依存という言葉は、もともと1970年代のアメリカで使われ始めました。言葉が生まれた背景には、アルコール依存症の夫とその妻たちの関係性があります。
たとえば、アルコール依存である夫の世話を焼き献身的に支えるものの、夫はますます酒に溺れてアルコール依存から抜け出せないといった具合に、妻が依存症の維持に手を貸しているケース。
-
妻が世話を焼き過ぎて、当事者である夫がアルコール依存の問題に直面しない
-
アルコール依存の夫の犠牲者として、悲劇のヒロインを演じている妻夫の失敗の後始末をし続けて、世間にアルコール依存であることを知られないようにふるまう
妻は依存症の夫に必要とされていることに、自身の存在価値を見出しているため、夫がアルコール依存症でなくなると困るのです。つまり、妻も間接的にアルコールに依存している、共依存であることが考えられます。
依存症には、アルコールやギャンブル、薬物などがありますが、共依存はわかりやすく言うと人との関係性の依存。人は誰しも支え合って生きているものですが、度を超えてお互いに過剰に依存し合う関係性になると、共依存と呼ばれる状態に陥るのです。
参照:e-ヘルスネット|共依存
共依存の核となる5つの症状

共依存やトラウマの治療施設「メドゥズ」のディレクターを務めるピア・メロディ氏によると、共依存には5つの中核症状があるとされています。
-
自尊心の問題:人と比べて上か下かという基準を頼りに生きようとする、内的な価値の手がかりがない
-
境界の問題:適切な境界線の引き方がわからない、壁を作って孤立したり境界がないまま相手に侵入されたりする現実性の問題: 完璧でないとダメで少しの間違いも許せない白黒思考、感情は揺れ動くものだという現実を認められない
-
依存の問題:人に頼らず何でも自分でしようとするか完全に人に頼ってしまうといった具合に、頼ることのバランスが悪い
-
中庸の問題:自分の衝動や欲求を吟味できない、即行動に移したり我慢して抑え過ぎたりする
共依存といっても、その背景にはさまざまな問題が複雑に絡み合っていることがわかります。
共依存に陥る原因は?

共依存に陥る主な原因は、以下の3つです。
-
家庭環境
-
自己肯定感が低い
-
アダルトチルドレン
育った家庭環境に問題がある場合や、アダルトチルドレンであることも、共依存の原因になります。また、成長過程における経験から、自己肯定感が育まれなかった場合に共依存に陥ることも。ここからは、共依存に陥る主な原因について深掘りしていきましょう。
家庭環境
幼少期にいわゆる「機能不全家族」と呼ばれる環境で育った場合、共依存に陥るケースがあります。機能不全家族とは、具体的には虐待やネグレクトなど身体的・精神的ダメージを与えることが日常化している家族のこと。また、子どもに対して無関心であることや、反対に過度な期待をかけることも精神的ダメージを与える要因になります。
機能不全家族でなくても、家庭内で強い人が支配していて自由に意見が言えない、安心できないといった環境も共依存につがる原因です。
人格形成において大切な時期に健全な家庭環境で育っていないことは、成長してから人間関係に問題を抱えたときに共依存に陥る原因となります。
自己肯定感が低い
幼少期に家庭内で褒められた経験がない、学校でいじめられたといった経験から、自己肯定感が育まれていないことがあります。また、容姿にコンプレックスがある場合、受験や恋愛での失敗が自己肯定感の低さにつながることも。
そのまま大人になったとき、自己肯定感が低いことから常に人に見捨てられる不安を抱えていたり、自分に欠けている部分を埋めようとしたりして共依存に陥る原因になります。
関連記事:自己肯定感とは?低い人の特徴や高める方法をわかりやすく解説
アダルトチルドレン
幼少期に家庭内で受けた心的外傷によって、トラウマを抱えたまま大人になった人のことをアダルトチルドレンと呼びます。アダルトチルドレンが生まれる背景には、先述の機能不全家族という家庭環境がありますが、アダルトチルドレンや機能不全家族で育った子ども全員が共依存に陥るわけではありません。
しかし、機能不全家族で育った場合、成長してから愛着障害や人格障害、うつ病などにつながるケースも多く見られ、共依存に陥る原因のひとつにもなり得るのです。
関連記事:アダルトチルドレンとは発達障害?診断やカウンセリング治療を解説
共依存に陥りやすい人の特徴

共依存に陥りやすい人には、その資質や行動パターンに特徴があるようです。心当たりがある人は、テキサス工科大学のフィッシャー氏とスパン氏により共同開発されたチェックリストで確認してみましょう。
-
褒められても素直に受け入れられない
-
断わることができない
-
自分で決断することが苦手
-
人間関係で巻き込まれやすい
-
相手が一人でできることでも手伝ってしまう
-
「こうあるべきだ」と思いやすい
-
なんでも自分のせいだと思う
-
周囲の環境次第で浮き沈みが激しくなる
-
尽くしても、報われない
-
1人でやっていく自信がない
-
人間関係でつらいと感じやすい
-
「本当の自分」を出せない
-
同じことの繰り返しをしてしまう
-
つい周りにあわせてしまう
-
時々、恐怖や切迫した感覚がある
-
自分のことより人のこと
共依存とは、最初に解説したとおり人との関係性の依存です。このチェックリストに多く当てはまる項目があっても、必ずしも共依存に陥っているとは限りません。あくまでも、共依存の可能性や傾向についての目安となるものです。
共依存に陥りやすい関係

共依存に陥りやすい主な関係には、以下の3つがあります。
-
親子関係
-
夫婦・カップル
-
職場の人間関係
親と子ども、夫婦や恋愛関係にあるカップル、職場における上司と部下の関係などで、共依存に陥りやすいとされています。お互いの関係性において「相手がいなくなったら困る」という状況に陥るのが共依存。ここからは、それぞれの関係性において具体的に見ていきましょう。
親子関係
親子関係における共依存では、親が子どもに対して過度に干渉したり、行動を制限したりすることにより「親がいないと困る」という状況をつくることで、子どもの自立を妨げています。子どもは「自分は親がいなければ何もできない」という思い込みを持ち、親は子どもが常に親を頼ってくることに存在意義を見出して共依存に陥るのです。
夫婦・カップル
恋愛関係にあるカップルの共依存には、いくつかのパターンがあります。ベースとなるのが恋愛依存症と回避依存症です。恋愛依存症は、恋愛感情を抱く相手がいると充実感を感じて、恋愛をしていないと満たされないタイプです。
対して回避依存症は、他人と深い人間関係を築くことが苦手であるため、縛られることに息苦しさを感じて、相手から離れてしまうタイプ。
恋愛依存症同士の夫婦やカップルでは、お互いに依存し合って「一人になりたくない」という不安から相手への束縛が強くなる傾向があります。恋愛依存症と回避依存症の夫婦やカップルで多いのは、一方は相手に尽くしすぎ、もう一方は尽くされることに慣れて結果として共依存に陥るケースです。
恋愛依存症の場合は相手に嫌われたくないあまり、相手の要求をすべて満たそうとして自分が我慢していることが多いようです。
職場の人間関係
職場において共依存に陥りやすい関係は、いつまでも独り立ちできない部下と頼られたい上司の組み合わせです。一見問題がない関係性に見えても、上司は指導の目的が部下の成長ではなく自己充足となっています。
一方で、部下は、わずらわしさを感じながらも、上司の言うことさえ聞いておけば間違えないという安心感から常に上司の指示を待っている状態。この状況は、お互いの存在がないと困るという共依存に陥っているといえます。
共依存の克服方法

共依存には特効薬のような治療方法はありませんが、いくつかの行動を起こすことで徐々に状況を改善できます。共依存の主な克服方法は、以下の4点です。
-
小さなことでも自分自身で判断する
-
自分の生い立ちを振り返る
-
グレーゾーンを作る
-
カウンセリングを受ける
自分自身で小さなことから行動や思考を変えたり、共依存の原因を明確にしたりすることが大切です。また、共依存に陥っていると客観的な視点で物事を見るのは難しいため、専門家に適切なアドバイスを求めるのもよいでしょう。
小さなことでも自分自身で判断する
日常生活には、決定しなければならないことがたくさんあります。献立は何にするのか、休日はどこに出かけるか、些細なことでもそれを誰かの判断に頼るのではなく、自分で判断することを習慣にしていきましょう。「自分のことは自分で判断することができる」「自分をコントロールできる」という経験を増やしていくことが大切。
自分の生い立ちを振り返る
共依存に陥ってしまう原因は、子どもの頃の家庭環境に多く見られます。生い立ちを振り返って、家族や家庭環境など子どもの頃のことを、ノートに書き出してみるのも共依存の克服に効果的です。子どもの頃の経験や感じていたことを明確にしてみることで、共依存になった背景が見えてくるかもしれません。
グレーゾーンを作る
共依存に陥りやすい人の傾向に「〇〇であるべき」「こうでなければいけない」といった思考(白か黒か・0か100かなど)があります。凝り固まった思考を変えてみて、白か黒かだけではなく、妥協点や中間点のグレーゾーンを意識してつくってみるとよいでしょう。
カウンセリングを受ける
共依存は関係性が濃い状態のため、客観的に物事を見られる専門家からアドバイスをもらい、健全な関係性を取り戻すのも効果的な克服方法です。外出が難しい場合や面と向かって話すのが難しい人は、オンラインカウンセリングがおすすめです。
オンラインカウンセリングには、以下のようなメリットがあります。
-
場所や時間に融通が利く(外出不要、スマホがあれば利用できる)
-
カウンセラーを複数の中から選べる(事前に資格、性別、得意分野などを把握して依頼できる)
「こころケア」には、医療機関での臨床経験があるカウンセラーが在籍しており、豊富な経験から適切なアドバイスができるため、安心してご利用ください。
まとめ
共依存の原因はさまざまで、遠い記憶をたどるような幼少期に原因があるケースも考えられます。また、知らず知らずのうちに共依存に陥っていて、本人は気づいていない間に深刻な状況になっていることも。もしこの記事を読んで、自分が共依存かもしれないと感じたら、早目に対処することが大切です。自分自身で対処するのが難しいようなら、一度オンラインカウンセリング「こころケア」を利用してみてはいかがでしょうか。
記事監修
公認心理師 櫻井 良平

国家資格
- 公認心理師
- 精神保健福祉士
- キャリアコンサルタント
- 社会福祉士
- 保育士
所属学会等
- 日本公認心理師協会
- 日本公認心理師学会
- 日本認知療法・認知行動療法学会
- 日本発達障害支援システム学会
(第17回研究セミナー・研究大会において学会賞受賞)
略 歴
- 医療機関や民間のセンター等での対面・電話・オンラインカウンセリング経験が豊富
- 認知行動療法にかかる厚生労働省・国立研究機関主催研修を修了
- 第一線の専門家に師事し、精神分析療法、解決志向短期療法、愛着理論、応用行動分析学等を研究
- 教育・心理・社会保障・保健医療分野における国内外の国際協力プロジェクトへの従事経験を持つ
(開発途上国における「育児・子育て手法」「発達アセスメント・支援ツール」「知能検査」の開発・普及プロジェクト等)